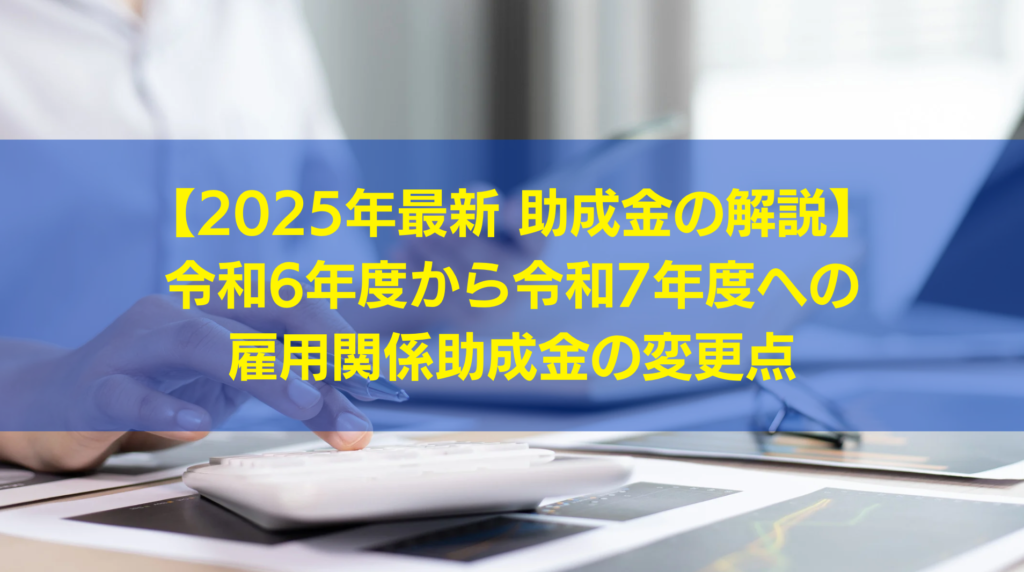【2025年最新 助成金の解説】令和6年度から令和7年度への雇用関係助成金の変更点
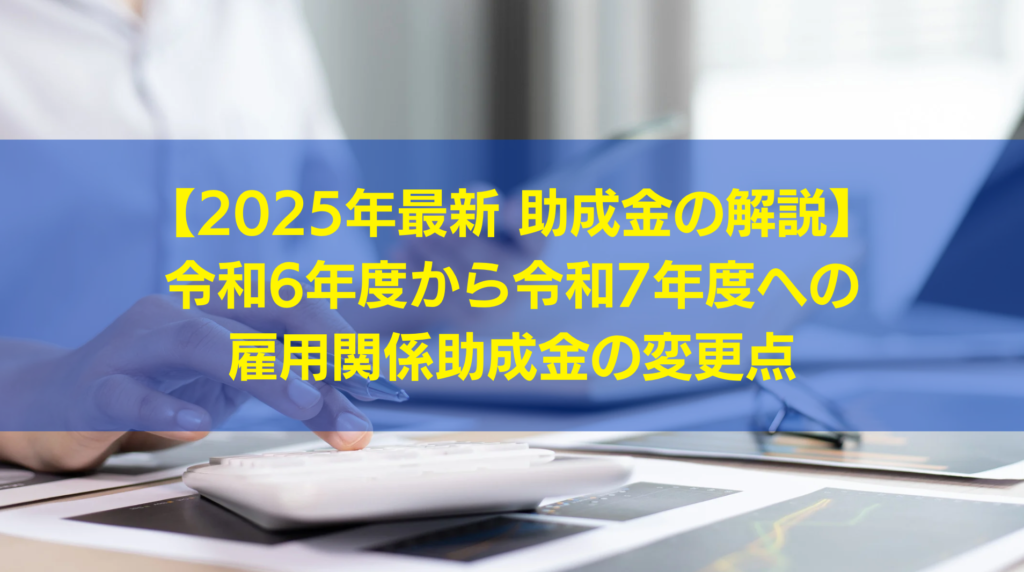
はじめに
令和7年度の雇用関係助成金について、厚生労働省より改正省令案が公表されました。雇用関係助成金は、企業が雇用や人材育成に関して行うさまざまな取り組みに対して経済的支援を行う制度であり、雇用保険法や労働施策の総合的な推進に関する法律を根拠としています。
今回の改正では、これまで利用されてきた助成金コースの一部廃止・統合や、新設コースの追加、要件の見直しなどが盛り込まれています。特に高齢者雇用、育児・介護と仕事の両立、高度なリスキリング(職業転換やスキル向上)など、近年大きく注目されている分野に関しては、より利用しやすい形に整備される一方で、利用実績が少なかったコースが統合あるいは廃止される動きもみられます。
本記事では、令和6年度の制度と比較しつつ、変更点を中心に詳しく解説いたします。実際に助成金を活用する企業や、これから助成金の利用を検討している皆様が押さえるべきポイントを整理しながら紹介していきます。
改正の背景と全体概要
改正の背景
厚生労働省が今回の助成金改正を行う背景には、主に以下のような課題・目標があります。
- 高齢化社会への対応
少子高齢化が進む日本では、65歳以上の労働者が増加しています。そのため、高齢者が長く働き続けられる環境づくりを推進する必要があり、雇用制度や助成金を通じた支援が拡充・見直しされます。
- 育児・介護との両立支援強化
働きながら子育て・介護を行う労働者が増えており、企業にも柔軟な働き方や休業制度の整備が求められています。従来の両立支援助成金に加えて、新たなコースや改正が行われました。
- 不安定就労者や失業者の再就職促進
経済状況や企業の人手不足などにより、非正規や不安定雇用の労働者が増加しています。これらの労働者が正規雇用へ転換しやすい環境整備や、失業者の早期再就職を促すための制度設計が進められています。
- 技能向上やリスキリングの推進
労働市場の変化が激しい現代では、企業や労働者自身が継続的にスキルアップや職業訓練を行うことが不可欠です。人材開発支援助成金をはじめとする制度全般を見直し、より使いやすく、効果的な支援を目指しています。
全体概要
今回の改正では、以下のような主な変更が行われる予定です。
- 既存コースの統合・廃止
「早期再就職支援等助成金」や「特定求職者雇用開発助成金」の一部コースなど、利用実績が少ない、あるいは他の助成金で代用可能なものが廃止または統合されます。
- 要件の緩和・見直し
「65歳超雇用推進助成金」における支給要件の簡素化、「特定求職者雇用開発助成金」の申請手続きの簡略化など、企業が利用しやすいよう要件が見直されるケースも多く見られます。
- 新設コースの追加
中高年層(35歳以上60歳未満)の不安定就労者向けコースや、「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金」など、新たな支援ニーズに対応するためのコースが登場します。
- 助成金支給額や助成率の引き上げ
「人材開発支援助成金」や「キャリアアップ助成金 賃金規定改定コース」などでは、一定の要件を満たすことで支給額や助成率が上がるなど、より高い支給額が見込める改正が実施されます。
それでは、以下で各助成金ごとの詳細を解説していきましょう。
早期再就職支援等助成金
令和6年度の概要
令和6年度においては、企業の事業規模縮小・廃業などにより離職を余儀なくされた労働者を再就職支援会社(アウトプレースメント事業者)等のサポートのもとで早期に再就職させる取り組みや、それらの離職者を雇い入れた事業主に対する助成が行われていました。さらに、雇入れ後に行う**OJT(職場内訓練)やOFF-JT(職場外の研修)**などの教育訓練についても、一定条件のもと追加助成が受けられる仕組みがありました。
令和7年度の変更点
令和7年度では、この早期再就職支援等助成金のうち、「雇入れ支援コース」における受入れ人材育成型訓練への助成が廃止となります。背景には以下の理由があります。
- 同種の訓練に対しては、人材開発支援助成金(旧「職業能力開発促進法」に基づく助成金)など他の助成金でも利用可能であること
- 過去の利用実績を見た際に、それほど多くの事業主が活用していなかった点
そのため、これまで「早期再就職支援等助成金」での訓練助成を検討していた企業・事業主の方は、令和7年度以降は人材開発支援助成金の各コースを活用するか、もしくは同一の助成金制度内でも訓練以外の部分の助成を利用する形へシフトすることが求められます。
65歳超雇用推進助成金
令和6年度の概要
- 高齢者の雇用安定や就業促進を目的として設けられた助成金です。日本の高齢化社会が進むなか、65歳以上まで働き続けられる仕組みを整備する企業に対して支給されます。主なコースは以下の3つでした。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 企業が定年を65歳以上へ引き上げたり、定年制の廃止、あるいは希望者全員を対象とした継続雇用制度を導入した場合などに助成
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢労働者向けの賃金制度や健康診断制度など、雇用管理制度の整備を行った場合に助成
- 無期雇用転換コース
令和7年度の変更点
今回、大きな改正点となるのが**「65歳超継続雇用促進コース」における支給要件の簡素化**です。具体的には、これまで支給対象事業主と認められるためには、
「高年齢者雇用安定法を遵守した状態が6か月以上継続していること」
といった要件が存在しました。しかし、これが令和7年度から削除される見通しです。つまり、
高年齢者雇用安定法に違反している就業規則(例:65歳までの継続雇用制度が規定されていない)を持つ企業であっても、計画申請や支給申請の時点で同法を遵守する形に改正すれば、助成金の支給対象となる
ということです。
制度改正の背景
高齢者が就労を継続しやすい社会を実現するためには、中小企業や小規模事業所を中心により柔軟かつ迅速に制度変更を行ってもらう必要があります。これまでの「まずは6か月以上の遵守実績を積まないと助成申請ができない」という要件は、少々ハードルが高く、制度変更のタイミングを逸してしまう企業も少なくありませんでした。
そこで、今回の改正では、違反状態を解消する意思を持って就業規則を改正し、適正に運用しようとする企業に対して、早い段階から助成が受けられるようになったわけです。この改正によって、高齢者の雇用安定策に取り組む企業が今後さらに増えることが期待されます。
特定求職者雇用開発助成金
令和6年度の概要
「特定求職者雇用開発助成金」は、生活保護受給者・高齢者(60歳以上)・障害者など、就職が困難な求職者を新たに雇い入れ、一定期間継続雇用する事業主に対して助成金が支給される制度です。雇用機会に恵まれない人々の就労を後押しすることで、社会的・経済的なセーフティネットを強化することを目的としています。
令和7年度の変更点
生活保護受給者等雇用開発コースの申請手続き簡略化
令和7年度では、生活保護受給者や母子家庭の母などを雇い入れた事業主に対する「生活保護受給者等雇用開発コース」について、申請手続きの簡素化が図られました。たとえば、必要書類の削減や電子申請手続きの更なる拡充などが想定されています。これによって、従来よりもスピーディーに手続きが進められる見込みです。
就職氷河期世代安定雇用実現コースの廃止
近年、大きく打ち出されていた**「就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金」**が廃止されました。就職氷河期世代(概ね1993年から2004年頃に学校卒業期を迎えた世代)を支援するための特別な助成コースとして運用されていましたが、対象世代の就労支援施策が他の仕組みへと移行していく流れ、及び一部重複が生じていた点などが廃止の理由とされています。
「中高年層安定雇用支援コース助成金(仮称)」の新設
就職氷河期世代コースが廃止される代わりとして、**「中高年層安定雇用支援コース助成金(仮称)」**が新設されます。対象となるのは「35歳以上60歳未満の不安定就労者」で、支給金額は以下のとおり予定されています。
この不安定就労者には、派遣社員や有期契約社員、アルバイト・パートなどの非正規雇用で、なおかつ一定条件を満たす人が該当すると考えられます。正式な条件は今後公表される詳細資料を確認する必要がありますが、一般的には雇用保険の被保険者要件を満たす新規雇用で、かつ当該労働者が就業継続することで安定した雇用に結びつくような場合に助成が受けられる仕組みとなるでしょう。
トライアル雇用助成金
令和6年度の概要
トライアル雇用助成金は、職業経験が不足していたり、就職困難者として位置づけられている求職者を一定期間(原則3か月)試行的に雇用し、適性を見極めたうえで本採用につなげる制度です。企業としては、試行的に雇用しながら労働者のスキルや職場適応を確認でき、労働者にとっては再就職へのハードルが下がるメリットがあります。
令和7年度の変更点
今回の改正では、支給年齢の上限を60歳未満に見直しが行われました。これまでは60歳以上も支給対象となっていましたが、高齢者の雇用対策は「65歳超雇用推進助成金」など他の助成金との重複も考慮した結果、トライアル雇用助成金としては60歳未満に対象を絞る方向性に改められます。
これにより、高齢者の雇用支援が一元化される一方、若年~中年層を中心とした就職困難者支援としてのトライアル雇用がより明確化されるといえます。
両立支援等助成金
両立支援等助成金は、育児や介護を行う労働者が安心して仕事を続けられる環境を整備する企業に対し、一定の経済的支援を行う制度です。育児休業や介護休業の取得、短時間勤務制度の導入など、労働者のライフステージに合わせて柔軟な働き方ができるよう取り組む企業が増えています。
育児・介護休業関連の改正
令和6年度までの流れ
令和6年12月の補正予算では、「出生時両立支援コース」の一部見直しや「育休中等業務代替支援コース」の拡充が行われました。出生直後の育児休業取得を企業が推奨し、仕事と子育ての両立を実践できる社会を目指す動きが強調された時期でもあります。
令和7年度の変更点
- 介護休業の助成要件
- 「合計5日以上」から「連続5日以上」に変更
これは、断続的に取得した休暇ではなく、まとまった期間をしっかり取得して介護と向き合う必要性が高いと判断され、制度設計が見直されたものと考えられます。
- 助成金の支給タイミング
- 「休業取得時と職場復帰時の分割支給」から「職場復帰時の一括支給」へ変更
企業にとっては、一時的に資金繰りがタイトになる可能性はあるものの、行政側としては、実際に復帰までの流れをしっかりと確認したうえで助成を行うことで、制度の適正運用を確保したい意図がうかがえます。
「柔軟な働き方制度選択コース」の改正
厚生労働省の資料によれば、令和7年10月の改正に伴い、「育児・介護休業法」改正法の施行と足並みをそろえる形で、「柔軟な働き方制度選択コース」の要件が変更されます。具体的には、
- 現行:柔軟な働き方選択制度(在宅勤務制度・フレックス制度・短時間制度など)を2つ以上導入した場合に支給
- 改正後:柔軟な働き方選択制度などを3つ以上導入した場合に支給
という具合に、導入すべき制度の数が増える予定です。これは、従来から推進されてきたテレワークやフレックスタイム制などの整備をさらに広げようとする狙いがあります。また、子の看護等休暇を有給扱いにするなど、より充実した制度を構築することで、働く親世代や介護を担う労働者を支援しようという方向性です。
子の看護等休暇の有給休暇支援の独立助成金
今回、子の看護等休暇を有給化する企業に対する支援が強化され、独立した助成金として設けられる見通しです。これにより、小さな子どもを抱える労働者が看護の必要がある場合、気兼ねなく休暇を取得できる環境が整備されることが期待されます。
「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金」の新設
同じく厚生労働省の資料により、**「不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース助成金」**が新設されることが発表されています。不妊治療のための通院や休暇取得、あるいは女性特有の健康課題(生理休暇や更年期障害への配慮など)に対応する制度を整えた企業を助成するものです。少子化対策の一環として、働く女性が治療と仕事を両立しやすい就業環境を整備することが強く求められている背景がうかがえます。
人材確保等支援助成金
令和6年度の概要
「人材確保等支援助成金」は、労働環境の改善や雇用管理制度の整備などを行い、企業が優れた人材を確保し、長期就業につなげるための取り組みに対して支給される助成金です。ただし、令和6年度までは新規の計画申請が一時停止されていたため、実際に利用できる企業は限られていました。
令和7年度の変更点
- コースの統合
- 「雇用管理制度助成コース」が「雇用管理制度・雇用環境整備助成コース」に統合
- さらに「人事評価等改善コース」も統合される見込み
これらの統合によって、雇用管理や人事評価制度の導入・改善、職場の環境整備といった取り組みを包括的にサポートする形が強化されるとみられます。
- 従業員の作業負担軽減のための機器導入が助成対象に
たとえば、工場や倉庫での作業効率を上げるためにロボット導入や省力化機器を導入し、作業負担を軽減する取り組みなどが助成対象となり得ます。これにより、生産性の向上と従業員の負担軽減を同時に実現し、人材定着や雇用の安定化へつなげる意図があります。
総じて、令和7年度からは新規の計画申請受付が再開されることが予想されるため、これから人材確保や職場環境の改善に本格的に取り組む企業にとっては注目度の高い助成金となるでしょう。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者(有期契約社員やパートタイマー、派遣社員等)の処遇改善やキャリアアップを支援するための助成制度で、様々なコースが存在します。ここでは特に大きな改正が入る「正社員化コース」と「賃金規定改定コース」についてみていきましょう。
正社員化コース
令和6年度の概要
令和6年度においては、非正規雇用から正規雇用(正社員)へ転換することで助成が行われる代表的なコースでした。多くの企業が利用しており、助成額の条件などが年度ごとに微調整されてきました。また、申請のタイミングが2期に分かれていることが特徴的で、年度途中に取り組んだ転換と年度末に近い時期に行った転換とで申請窓口や期日が異なるケースもありました。
令和7年度の変更点
- 支給対象者の適正化
これまで幅広く非正規から正社員化した労働者が対象となってきましたが、雇用期間や過去の雇用形態を基準に重点支援を行う対象者を明確化し、そもそも助成対象外となるケースが増える可能性があります。
- 例えば「通算雇用期間」や「過去5年間の正規雇用歴」の有無などによって、助成の可否や助成額が変わる仕組み
- 重点支援対象者以外の減額
重点支援対象者(不安定就労者)でない労働者を正社員化する場合の助成額が減額される見直しが行われます。これにより、企業としては重点支援対象者を優先的に正社員化することで、高い助成を得られるインセンティブが働くようになるでしょう。
- 新卒者は一定の期間対象外
新卒で有期契約等として入社した後、すぐに正社員転換を行う場合は助成金の趣旨にそぐわないとして、一定期間は助成対象外とされます。具体的な期間は今後の詳細要件次第ですが、例えば「入社後○ヶ月程度は助成対象にならない」といった形で設定される見込みです。
- 不安定雇用者の定義
「雇入れから3年未満の人で、過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下、かつ過去1年間に正規雇用として雇用されていない」など、相対的に不安定な立場にいると判断される労働者が重点支援対象となります。そういった方々を正社員化することにより、より高い助成が受けられるようになります。
総合的に見ると、企業がキャリアアップ助成金を活用して正社員化を進める際は、対象者の選定が令和6年度よりも慎重に行われる必要があると言えます。特に人数を多く転換する場合は、だれが重点支援対象に該当し、どの程度の助成が得られるのかを事前に確認・把握しておかなければなりません。
賃金規定改定コース
令和6年度の概要
非正規雇用労働者の基本給や賃金テーブルを一定以上引き上げる、あるいは賃金規定そのものを改定して待遇を改善した場合に支給されるコースです。中小企業を中心に、最低賃金の上昇や人材確保競争の激化に対応するために利用されてきました。
令和7年度の変更点
- 賃金引上げ率の区分が拡大
従来は「2段階」だった区分が「4段階」に細分化され、6%以上の引上げを行った場合にさらに高額の助成を得られるようになります。最低賃金の大幅引上げが全国的に話題となるなか、企業努力をより強く後押しする設計といえます。
- 昇給制度新設の助成
令和7年度より、新たに昇給制度を初めて整備する事業主に対する助成が追加されます。例えば、従来は昇給制度がなかった企業が、年1回の定期昇給や職能評価に連動した昇給制度を導入することで、賃金規定改定コースの対象となり、助成が受けられる可能性が高まります。
人材開発支援助成金
令和6年度の概要
人材開発支援助成金は、企業が従業員に対して実施する職業訓練や教育研修などの人材育成施策を支援する制度です。コースとしては以下が代表的です。
- 特別育成訓練コース
- 一般訓練コース
- 有期実習型訓練
- 中小企業向けのオーダーメイド研修
- リスキリングや新分野展開向け(事業展開等リスキリング支援コースなど)
- 人への投資促進コース
令和7年度の変更点
- 賃金助成額の引き上げ
- 「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」の賃金助成額が引き上げられます。
企業が研修期間中に支払う従業員の賃金に対して支給される助成額が増えるため、より積極的に従業員を研修に送り出しやすくなると期待されます。
- 正規雇用転換等を促進する高率助成の廃止
有期契約労働者等を対象に、訓練実施後に正規雇用へ転換すると高い助成率が適用される仕組みが廃止されます。これは、キャリアアップ助成金や他の制度との重複を見直す形で行われるものです。
- 有期契約労働者等に対する訓練機会確保の助成率引き上げ
- 有期契約労働者等に訓練を実施した場合、経費助成率が70%(賃上げをした場合は85%)に引き上げ
- 正規雇用転換を行う場合の要件が一部変わり、逆に助成率は高まる
これにより、短期契約や非正規雇用の労働者に対しても積極的にスキルアップの機会を提供するインセンティブが企業に働きます。
- 有期実習型訓練の助成強化
- 正規雇用労働者等への転換等を行った場合に限定し、経費助成率が75%(賃上げをした場合は100%)に上昇
これは「有期実習型訓練」を行うことで、労働者の能力開発と安定雇用を同時に実現しようとする取り組みをさらに後押しするものです。
今回の助成金改正で押さえておきたいポイント
- 廃止・統合されるコースの確認
令和6年度まで利用していたコースが令和7年度からはなくなる、あるいは他のコースに吸収される場合があります。事前に「これまでと同じ条件で支給されるのか」をチェックする必要があります。
- 要件緩和による新たなチャンス
「65歳超継続雇用促進コース」における「高年齢者雇用安定法の遵守期間」の要件撤廃など、以前は要件を満たせなかった事業主が新たに申請できるようになるケースがあります。就業規則の整備も含めて、改めて検討してみましょう。
- 不安定就労者や中高年層への重点支援
「中高年層安定雇用支援コース助成金(仮称)」の新設など、35歳以上60歳未満で不安定な立場にある求職者の支援が強化されます。人材不足対策や多様な人材登用を検討している企業は、これらの新コースを積極的に活用するとよいでしょう。
- 両立支援制度のさらなる充実
育児・介護休業の助成金支給タイミングの変更や、「柔軟な働き方制度選択コース」の3制度以上導入要件、不妊治療両立支援コースの新設など、仕事と家庭の両立支援を強化する流れが顕著です。労働力確保だけでなく従業員の満足度向上にもつながるため、経営戦略として検討する価値があります。
- 人材育成・リスキリングの支援拡大
人材開発支援助成金の賃金助成率アップなど、従業員のスキルアップに積極投資する企業が有利になる仕組みが強化されています。事業拡大や新分野進出の足がかりとして、研修プログラムや教育計画を立案するのが得策です。
申請手続きにおける留意点
- 最新の公募要領・支給要件を必ず確認
本記事の内容は公表されている改正省令案や厚労省資料に基づく情報ですが、最終的な制度設計は年度末や令和7年度直前に確定する場合もあります。必ず厚生労働省や都道府県労働局の公式サイトで最新情報を確認しましょう。
- 就業規則や労働条件通知書の整備
助成金の支給要件を満たすためには、対象となる労働者の雇用形態や処遇を明確化し、それを就業規則や労働条件通知書に反映しておくことが非常に重要です。変更や改正があった場合は、労働基準監督署への届け出もお忘れなく。
- 計画届の事前提出
「キャリアアップ助成金」など一部の助成金では、計画届を雇用形態を転換する前や制度を導入する前に提出しなければならないコースが多いです。事後に申請しても支給対象外になることがあるので、早めに社会保険労務士や専門家へ相談することをおすすめします。
- 労働者への説明と合意形成
育児・介護休業やテレワークなど、新しい制度を導入する際には労働者や管理職への周知や合意形成が不可欠です。助成金ありきではなく、実際に働く現場で使いやすい制度を作るよう心がけることで、助成金の活用効果が高まります。
- 同時申請や併用可否の確認
企業が複数の助成金を同時に申請・受給することも可能ですが、重複支給が認められない場合もあります。たとえば、人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金の一部コースで支給対象が重なるなど、助成金同士の併用ルールをしっかり確認する必要があります。
まとめと今後の展望
令和7年度の雇用関係助成金の改正では、既存コースの統合や廃止、新コースの追加、支給要件の緩和または厳格化が複合的に行われます。改正の方向性としては、
- 高齢者雇用のさらなる促進(要件緩和や統合)
- 育児・介護など両立支援策の充実(女性・家庭支援強化、不妊治療支援など)
- 中高年層や不安定就労者への雇用創出支援
- 非正規から正規への転換や賃金引上げによる処遇改善
- 企業の人材育成・リスキリング支援の強化
といった点が挙げられます。これらの背景には、国として雇用の安定と労働市場の流動性確保をバランスよく図りたい思惑があると考えられます。
活用のポイント
- 助成金の申請は計画的に
多くの助成金が年度単位での予算枠を持っているため、早めの計画立案と届出が重要です。特に年度初めには申請が殺到し、予算枠が消化される可能性があるコースもあるので注意しましょう。
- 社内の体制整備・専門家活用
助成金申請には書類作成や労務管理、就業規則改定など幅広い業務が伴います。社内で専任担当を置くか、社会保険労務士や各種専門家と連携しながらスムーズに進めるのが望ましいです。
- 自社の課題解決に直結する選択を
助成金を受給すること自体が目的化してしまうと、制度改正や運用に振り回されやすくなります。自社の経営戦略や人事ポリシーに合致した助成金を選択・組み合わせることで、長期的な効果を得ることができます。
今後の展開
少子高齢化が進む日本において、労働市場は今後ますます流動化が進むと予想されます。国としても、人材の活用や生産性向上を促す施策をさらに充実させるでしょう。特に「AI時代への対応」「ジョブ型雇用の普及」「副業・兼業の普及」など新しい働き方との兼ね合いで、助成金の在り方も変化していく可能性があります。
また、人的資本経営への注目が高まり、企業の人材投資や育成施策が評価される流れも強まっています。令和7年度の改正を機に、改めて自社の雇用管理や人材戦略を見直し、助成金制度を活用しながら持続的な成長につなげていただければと思います。
終わりに
令和7年度の雇用関係助成金の改正では、既存助成金の大幅な見直しや新たな助成制度の導入が行われ、企業の人材戦略や働き方改革に活用しやすい形へとシフトしています。特に「高齢者雇用」「女性や子育て・介護と仕事の両立」「非正規の正規化」「人材育成・リスキリング」などが注目されており、こうした分野での取り組みを考える企業は、ぜひ最新情報をキャッチアップして申請を検討してください。
助成金の申請には、法令遵守・就業規則整備・労働者との合意形成など多くのプロセスが伴います。申請条件や支給要件は決して単純ではないため、実務対応には専門知識が必要となる場面も多いでしょう。自社の経営方針や現場の実情を踏まえながら、無理のない範囲で計画的に取り組んでいただくことが重要です。
企業が助成金をうまく活用し、従業員の働きやすい環境づくりや人材投資を推進することで、結果的に生産性向上や企業価値の拡大へとつなげられます。令和7年度の新制度が、御社の成長と雇用安定のための一助となれば幸いです。
もし不明点や詳細な手続きでお困りの際は、社会保険労務士や各種専門家へご相談いただくことをおすすめいたします。今後も最新の雇用施策情報をチェックしながら、より良い働き方と企業運営を実現していきましょう。